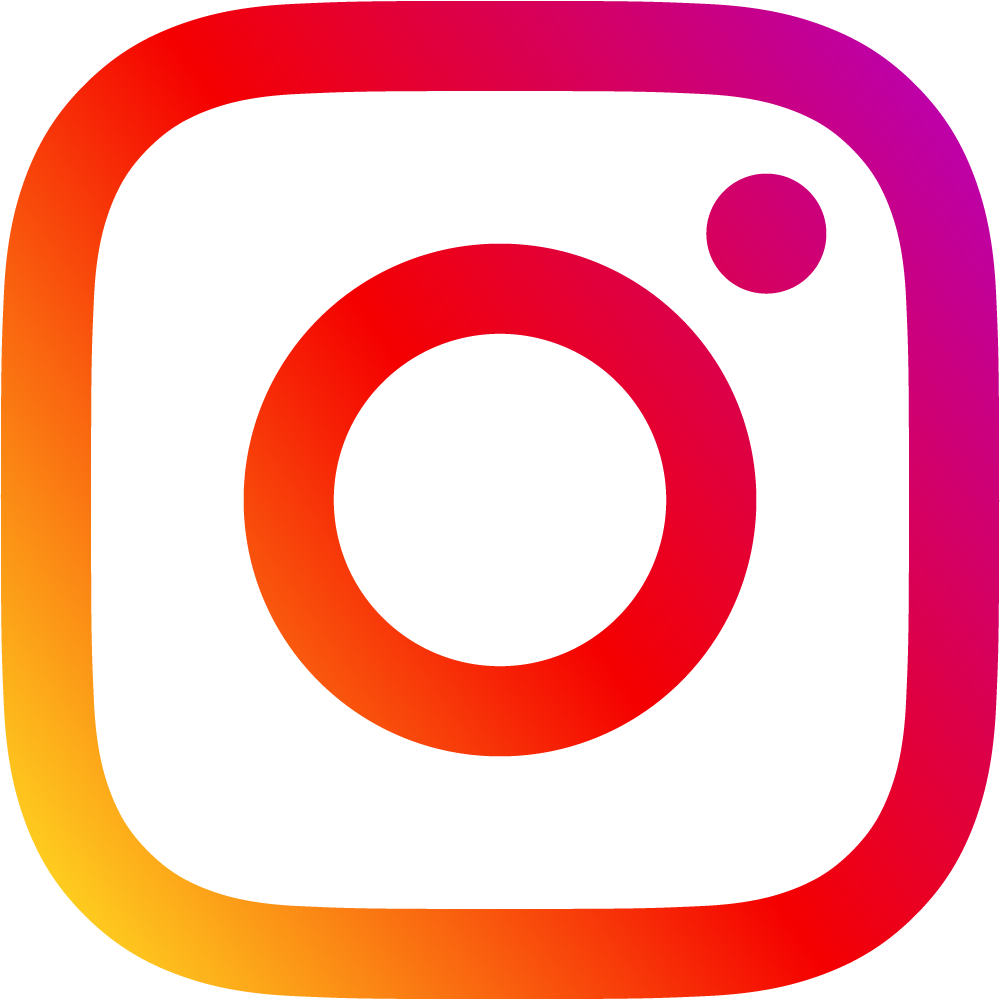失敗しない!ウッドデッキ塗料の選び方と種類をプロが徹底解説
はじめまして。株式会社プラッツ エクステリアプランナーの藤田です。
ウッドデッキの塗装をDIYで計画するとき、「どれを選べばいいの?」と塗料コーナーで立ち止まってしまう方は多いのではないでしょうか。
塗料にはたくさんの種類があり、種類を間違えると、塗った後すぐに剥がれてしまったり、期待した耐久性が得られなかったりします。
この記事では、DIY初心者の方でも迷わず最適な塗料を選べるよう、ウッドデッキ塗料の「浸透性」と「造膜性」、そして「水性」と「油性」という2つの基本分類を、プロの視点から徹底的に解説します。
塗料の選び方をマスターして、ウッドデッキを美しく長持ちさせましょう!
もし、ご自宅のデッキに最適な塗料選びに迷ったら、エクステリア専門会社 プラッツにご相談ください。
目次
1. 塗料の基本:ウッドデッキ塗料を選ぶ際に知っておきたい2つの分類
ウッドデッキ塗料を選ぶ際、専門的な情報が多くて混乱しがちです。
しかし、塗料の性質は大きく分けて、以下の2つの軸で分類できることを覚えておけば、失敗は格段に減ります。
<ウッドデッキ塗料の2大分類>
1. 保護の方法による分類(仕上がり):浸透性 vs 造膜性
塗料が木材の表面に膜を作るか、内部に染み込むか、という保護の仕方による分類です。
仕上がりの見た目や、次回の塗り直しの手間が変わってきます。
2. 主成分による分類(取り扱いやすさ):水性 vs 油性
塗料の主成分が水(水で薄められる)か、溶剤(シンナーなど溶剤で薄められる)か、という分類です。
においの強さや、乾燥時間、耐久性に違いがあります。
この2つの分類を理解することが、ご自身のウッドデッキの木材の種類や、ご希望のメンテナンス頻度、そして作業環境に合った最適な塗料を選ぶための第一歩となります。
2. 浸透性塗料 vs 造膜性塗料:メリット・デメリットと適したデッキ材
塗料がウッドデッキをどのように保護するか、という観点で、浸透性(しんとうせい)と造膜性(ぞうまくせい)の違いを詳しく見ていきましょう。
1. 浸透性塗料(ステイン系)
特徴: 木材の内部に深く染み込み、木そのものの呼吸を妨げません。表面には塗膜(膜)を作りません。
メリット:
- 木目や木の質感を活かした自然な仕上がりになる。
- 塗膜が剥がれないため、塗り直しの際、古い塗料を剥がす作業(サンディング)がほぼ不要で手間がかからない。
デメリット:
- 撥水性や耐久性が造膜性に劣るため、塗り直し頻度が高くなる(一般的に1~3年)。
適したデッキ材: 天然木全般。特にハードウッドなど木目を強調したい場合。
2. 造膜性塗料(ペンキ系・ニス系)
特徴: 木材の表面を樹脂の硬い塗膜で覆い、外部からの水や紫外線をシャットアウトします。
メリット:
- 撥水性・防水性が高く、耐久性に優れる(一般的に3~5年と長持ちする)。
- デッキの色を大きく変えたり、完全に覆い隠したりできる。
デメリット:
- 塗膜が劣化して剥がれる際、見た目が悪くなる。塗り直しの際、古い塗膜を完全に剥がす大掛かりな下地処理が必要になる。
適したデッキ材: 耐久性を重視したい場合や、デッキの色を大きく変えたい場合。
DIY初心者には、塗り直しが簡単な浸透性塗料をおすすめすることが多いです。
3. 水性塗料 vs 油性塗料:取り扱いやすさ・耐久性・環境への配慮
次に、塗料を溶かす主成分の違いによる分類を見ていきましょう。これは、作業のしやすさや安全性に直結する重要なポイントです。
1. 水性塗料
特徴: 主成分が水で、水で薄めたり、使ったハケを水で洗ったりできます。
メリット:
- 刺激臭が少ないため、ご近所への配慮が必要な場合や、小さなお子様がいるご家庭でも使いやすい。
- 引火性がなく、安全に取り扱える。
デメリット:
- 油性に比べて耐久性がやや劣る製品が多い。
- 乾燥時間が油性より長くなる傾向がある。
2. 油性塗料(溶剤系塗料)
特徴: 主成分がシンナーなどの有機溶剤で、塗料を薄める際や道具の洗浄には専用の溶剤が必要です。
メリット:
- 一般的に耐久性・撥水性・防腐性が高く、長持ちする製品が多い。
- 乾燥時間が水性より短い傾向がある。
デメリット:
- 特有の強いにおいがあるため、換気や近隣への配慮が必要。
- 引火性があるため、火気厳禁で取り扱いには注意が必要。
DIYでの手軽さを優先するなら水性、耐久性と仕上がりの良さを優先するなら油性を選びましょう。ただし、近年は水性塗料でも高性能な製品が増えています。

4. 長持ちさせるための重要項目!「防腐・防カビ効果」のチェックポイント
ウッドデッキを腐食から守り、寿命を延ばすために、塗料選びで最も重視すべきなのが「防腐・防カビ効果」です。
これは、塗料に木材の腐敗菌やカビ菌の繁殖を防ぐ薬剤が配合されているか、という点を示します。
<ラベルで確認すべきこと>
塗料の缶やパッケージには、必ずその塗料が持つ効果が明記されています。以下のキーワードがあるかチェックしてください。
- 木材保護塗料
- 防腐・防カビ効果
- 防虫効果(特に白蟻対策)
- 屋外木部用
これらの表示がない、いわゆる「ただのペンキ」のような塗料では、木材の表面を覆うことはできても、内部からの腐食を防ぐ力は期待できません。
特に、ウッドデッキの継ぎ目や木口(こぐち:木材の断面)といった水分を吸い込みやすい部分は、防腐・防カビ成分がしっかりと浸透することが重要です。
私が受けた相談でも、安価な塗料を選んだ結果、数年でデッキの根太(土台)が腐ってしまい、高額な修繕費用がかかってしまったケースがありました。
ウッドデッキの寿命を左右するのは、価格ではなく、この「保護性能」であることを忘れないでください。
5. 色選びのコツ:ウッドデッキの色が持つ印象と塗り替えのポイント
性能が決まったら、次は色選びです。ウッドデッキの色は、家の外観や庭の印象を大きく左右します。
<色選びの3つのヒント>
1. 外壁やサッシとの調和
ウッドデッキは、外壁やサッシの色とケンカしない色を選びましょう。濃い茶色(ブラウン)は、モダンな外壁にも、クラシックな外壁にも合わせやすい万能カラーです。
2. 明るい色 vs 暗い色
明るい色(ライトオークなど)は、庭を広く、開放的に見せる効果があります。一方で、汚れが目立ちやすいというデメリットもあります。
暗い色(ダークブラウンなど)は、汚れが目立ちにくく、デッキに重厚感や高級感を与えます。ただし、夏場は熱を吸収しやすく、デッキ表面が高温になりやすいという特性があります。
3. 紫外線による色褪せを考慮する
色が薄い塗料や透明な塗料は、木目を活かせますが、紫外線(UV)が木材に届きやすく、グレーに変色しやすい傾向があります。
紫外線から守るなら、顔料(色材)が多く含まれた濃い色の方が、UVカット効果が高く、色持ちが良くなります。
色見本だけで判断せず、実際に塗った時の濃さ(木材に染み込むため、見本より薄く見えることが多い)を想像しながら選びましょう。
6. よくある質問: 初心者におすすめのタイプは?塗料の量はどう計算する?
ウッドデッキ塗料に関する、DIY初心者の方からよく寄せられる質問にお答えします。
Q1. DIY初心者が最も失敗しにくい、おすすめの塗料タイプを教えてください。
A. 浸透性の水性塗料が最も扱いやすいです。
浸透性は、仮に塗りムラができても目立ちにくく、次回塗り直す際の下地処理も簡単です。
水性塗料は、刺激臭がなく、ハケやローラーを水で洗えるため、作業後の片付けも簡単です。最近は耐久性の高い水性塗料も増えているため、ホームセンターで探してみましょう。
Q2. 塗料の必要量はどう計算すれば失敗しませんか?
A. デッキの面積を測り、メーカーが示す「塗布量」を基に計算します。
塗料缶には「1缶で〇〇㎡塗れます」と記載されています。注意すべきは、この数値が「1回塗り」の面積である場合が多いことです。
ウッドデッキ塗装は基本的に二度塗りが必要なため、デッキの総面積の「2倍」を計算し、記載の塗布量で割って必要な缶数を求めましょう。少し多めに用意しておくと安心です。
Q3. 異なるメーカーや種類の塗料を混ぜて使っても大丈夫ですか?
A. 混ぜて使うのは基本的に避けてください。
水性と油性、浸透性と造膜性は、主成分や化学構造が全く異なります。混ぜると分離してしまい、塗料の性能が著しく低下したり、木材に密着しなくなったりする原因となります。
色を調整したい場合は、必ず「同じメーカー」の「同じ種類(水性なら水性など)」の塗料同士で行ってください。
まとめ
ウッドデッキ塗料の選び方には、「浸透性 vs 造膜性」「水性 vs 油性」という2つの大きな軸があります。
ご自身のデッキ材や、作業環境、そして希望するメンテナンス頻度に合わせて、この4つの特性を理解して選ぶことで、失敗は確実に防げます。
特に、ウッドデッキの寿命を延ばすために、パッケージに「防腐・防カビ効果」が明記されているか必ず確認してください。
「塗料選びに失敗したくない」「プロの視点で最適なものを選んでほしい」とお考えでしたら、ぜひ株式会社プラッツにご相談ください。
お客様のデッキに最適な塗料と、長持ちする塗装プランをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
プラッツの施工事例は こちら