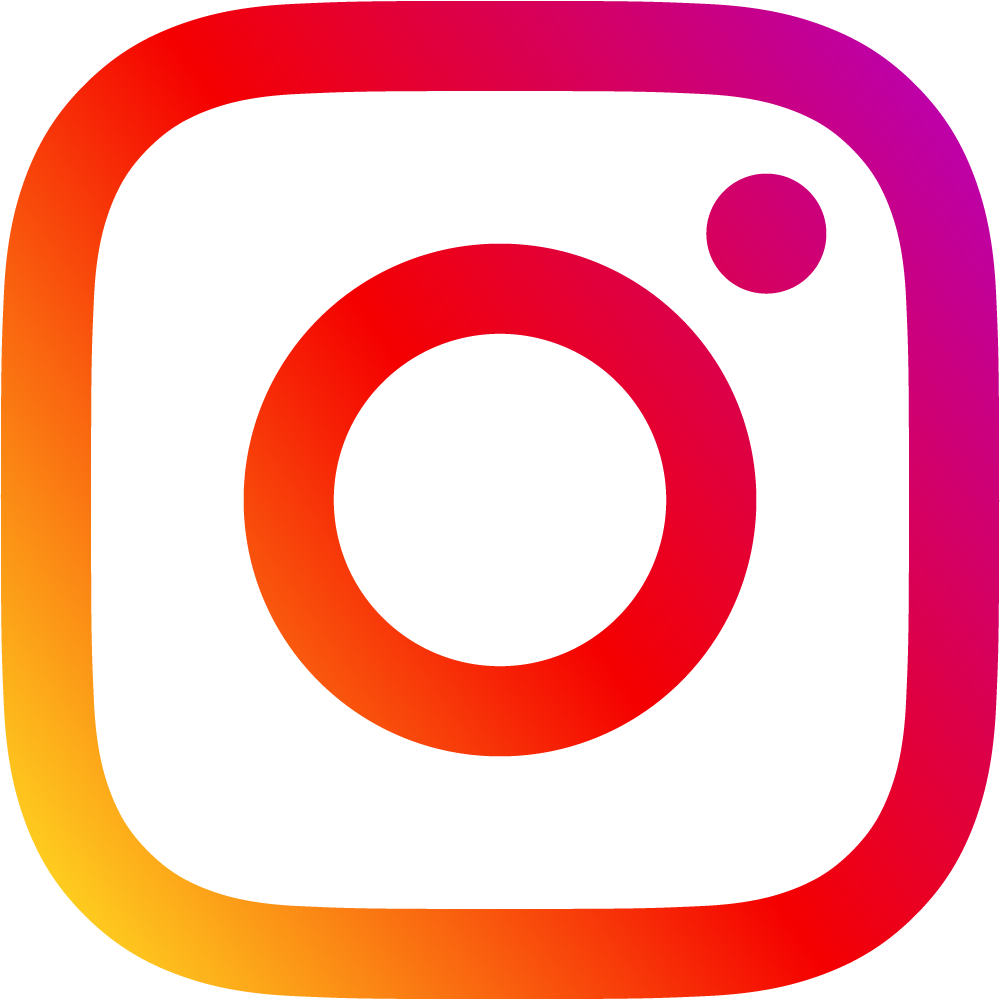【落葉樹の剪定】冬がベスト!種類別のやり方と失敗しないコツ
はじめまして、株式会社プラッツでエクステリアプランナーをしております藤田と申します。
「庭のモミジが伸びてきたけど、いつ切ればいいんだろう?」
「落葉樹の剪定は冬がいいって聞くけど、具体的にどうすれば…」
冬になり葉が落ちた庭木を眺めながら、剪定について考え始める方も多いのではないでしょうか。特にモミジやハナミズキといった「落葉樹」は、正しい時期に適切な手入れをすることで、その美しさを何倍にも引き出すことができます。
しかし、いざハサミを握ろうとしても、「どの枝を切ればいいの?」「切りすぎて失敗したらどうしよう」といった不安がよぎりますよね。
この記事では、そんなあなたのために、落葉樹の剪定に最適な「冬剪定」の具体的な方法を、プロの視点から徹底解説します。切るべき枝の見分け方から、樹種ごとの注意点、失敗しないためのコツまで、この一本で落葉樹剪定のすべてが分かります。
この記事を読み終えれば、きっと自信を持って、大切な庭木の剪定に臨めるはずです。もし、作業中に少しでも迷うことがあれば、私たちエクステリア専門会社 プラッツにご相談ください。
目次
1. なぜ冬?落葉樹の剪定が「休眠期」一択である理由
先日の記事でも触れましたが、落葉樹の剪定は、木が活動を停止する冬の「休眠期」(12月~2月)に行うのが大原則です。なぜ、この時期がベストなのでしょうか。その理由は、剪定する側と、される木の両方にとって大きなメリットがあるからです。
- 木への負担が最小限
休眠期の木は、人間で言えば深い眠りについている状態です。木の成長活動が完全に止まっているため、枝を切られてもダメージが少なく、体力の消耗を最小限に抑えられます。他の季節に剪定すると、木は傷を治そうと必死にエネルギーを使うため、大きな負担となり、時には枯れる原因にもなります。 - 枝の構造が一目瞭然
葉がすべて落ちているため、木の骨格となる枝の構造が隅々までよく見えます。どの枝が混み合っているのか、どの枝が不要なのかが一目瞭然で、完成形をイメージしながら作業を進められます。これは、DIYで剪定を行う上で非常に大きなアドバンテージです。
2. 剪定前に必ずチェック!切るべき枝と残すべき枝の見分け方
いざ木を目の前にすると、「いったいどの枝を切ればいいんだ?」と迷ってしまいますよね。そんな時は、まず「忌み枝(いみえだ)」と呼ばれる、木の成長や美観を損なう不要な枝を探すことから始めましょう。これらを取り除くだけでも、木は見違えるほどスッキリします。
代表的な忌み枝には、以下のようなものがあります。
- 徒長枝(とちょうし):他の枝より明らかに勢いよく、真上にまっすぐ伸びている枝。樹形を乱し、他の枝の養分を奪ってしまいます。
- 絡み枝・交差枝:他の枝と絡まったり、交差したりしている枝。見た目が悪いだけでなく、風で擦れてお互いを傷つけます。
- ひこばえ:木の根元から生えてくる細い枝。幹の養分を奪うため、見つけ次第、根元から切り取ります。
- 胴吹き枝(どうぶきえだ):幹の途中から直接生えている枝。樹形を乱す原因になります。
- 下り枝・逆さ枝:下向きに伸びたり、幹の中心に向かって伸びたりしている不自然な枝。
- 枯れ枝:文字通り、枯れてしまった枝。病害虫の温床になるため、必ず取り除きます。
これらの忌み枝を根元から切り取る「枝抜き剪定」が、落葉樹剪定の基本となります。
3. 【実践】美しい樹形を作る!落葉樹の基本剪定3ステップ
切るべき枝が分かったら、いよいよ実践です。以下の3ステップで進めると、スムーズに作業できます。
- Step1: 木から離れて全体を眺める
まずは木に近づかず、少し離れた場所から全体を眺めて、どんな形にしたいか、完成形のイメージを頭に描きます。どこが混み合っているか、全体のバランスを崩している枝はどれか、客観的に観察しましょう。 - Step2: 太い不要枝から切る
次に、先ほど覚えた「忌み枝」の中でも、特に太くて目立つものから切り始めます。太い枝を数本切るだけでも、全体の印象は大きく変わります。のこぎりを使い、枝の付け根から切り落としましょう。 - Step3: 細かい枝を整理して仕上げる
太い枝の整理が終わったら、今度は細かい枝に目を向け、全体のバランスを見ながら間引いていきます。枝と枝の間隔を均等にし、風や光が木の内部まで通るように「透かす」イメージで作業するのがコツです。やりすぎるとスカスカになってしまうので、時々木から離れて全体を確認しながら進めましょう。

4. 【樹種別】ここだけは押さえて!人気の落葉樹・剪定のポイント
落葉樹と一括りにしても、種類によって特性は様々です。ここでは人気の高い樹種の剪定ポイントをご紹介します。
自然な枝ぶりを活かす「モミジ」「アオダモ」
これらの木は、自然に伸びる柔らかい枝ぶりが魅力です。強く切り詰めすぎると、その良さが損なわれてしまいます。忌み枝を取り除く「枝抜き剪定」を基本とし、軽めに透かす程度にとどめましょう。
花芽を意識する「ハナミズキ」「ウメ」
花を楽しむ木は、花芽を切り落とさないことが最重要です。ハナミズキやウメの花芽は、冬には枝の先端に形成されています。枝を短く切り詰める「切り戻し剪定」をしすぎると、花が咲かなくなってしまいます。混み合った枝を根元から抜く剪定を中心に行い、枝先はなるべく残すようにしましょう。
5. これはNG!落葉樹の剪定でやりがちな失敗例と対策
- 失敗例1:切りすぎてしまう
夢中になって切っていると、気づけばスカスカの寂しい姿に…というのはよくある話です。一度切った枝は元に戻りません。
【対策】こまめに木から離れて全体のバランスを確認する癖をつけましょう。「ちょっと物足りないかな?」くらいで止めておくのが成功のコツです。 - 失敗例2:すべての枝先を切り詰めてしまう
大きさを揃えようとして、すべての枝の先端を同じ長さで切り詰めてしまうと、そこから不自然な枝が複数本伸びてしまい、かえって樹形が乱れます。
【対策】枝を短くしたい場合は、枝分かれしている付け根まで遡って切りましょう。
6. 【よくある質問】 落葉樹の剪定に関するQ&A
Q1. 太い枝を切りたいのですが、どこで切るのが正解ですか?
A1. 太い枝は、幹や別の枝から分かれている付け根の部分ギリギリで切るのが基本です。付け根にある、少し膨らんだ「ブランチカラー」という部分をわずかに残して切ると、切り口の治りが早くなります。幹と平行に、えぐるように切ってしまうのはNGです。切り口が大きくなる場合は、病原菌の侵入を防ぐために癒合剤(ゆごうざい)を塗っておくとより安心です。
Q2. 数年放置して大きくなりすぎました。一度に小さくしても大丈夫?
A2. いいえ、一度に強引に小さくするのは非常に危険です。木が急激な変化に耐えられず、枯れてしまう可能性があります。大きくなりすぎた木は、2~3年計画で段階的に小さくしていくのが鉄則です。1年目は不要な大枝を数本抜く程度にとどめ、翌年、翌々年の冬に徐々に理想の大きさに近づけていくのが安全な方法です。
Q3. 春先に枝から樹液が垂れてきました。これは問題ないのでしょうか?
A3. それは、木が休眠から覚めて活発に水を吸い上げ始めた証拠です。特にカエデ類などで見られる現象で、剪定時期が少し遅かったサインでもあります。少量であれば問題ありませんが、木に負担がかかっている状態ではあるので、やはり剪定は厳冬期(12月~2月)に終えておくのが理想です。
まとめ:冬の手入れが、春の芽吹きを美しくする
今回は、落葉樹の冬剪定について、その理由から具体的な方法までを詳しく解説しました。
- 落葉樹の剪定は、木への負担が少なく、枝が見やすい冬の休眠期がベスト。
- まずは樹形を乱す「忌み枝」を取り除くことから始める。
- 木から離れて全体を見ながら、少し物足りないくらいで止めるのが成功のコツ。
寒い冬の間に愛情を込めて手入れをすることで、木は春に美しい新緑で応えてくれます。その芽吹きを見たときの喜びは、自分で手入れをしたからこそ味わえる格別なものです。
この記事を参考に、ぜひ落葉樹の剪定にチャレンジしてみてください。もし、「この太い枝を切るのが怖い」「高すぎて自分では無理だ」と感じた場合は、決して無理をしないでください。そんな時は、私たち株式会社プラッツがお手伝いします。お客様の大切な庭木一本一本に最適な剪定をいたしますので、お気軽にご相談ください。
プラッツの施工事例は こちら