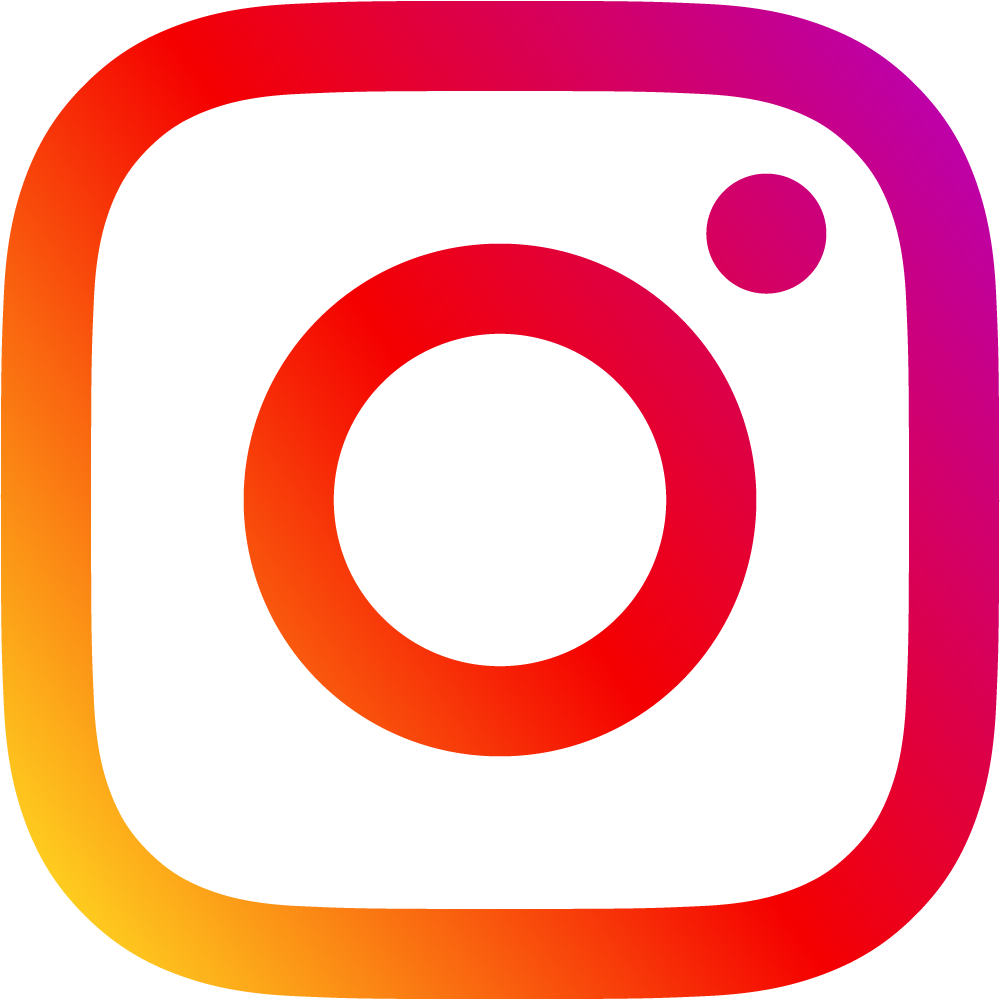庭木剪定の時期を解説!DIYで失敗しないコツ
はじめまして、株式会社プラッツでエクステリアプランナーをしております藤田と申します。
「庭の木、そろそろ自分で剪定してみたいな」
「でも、切る時期を間違えて枯らしてしまったらどうしよう…」
庭いじりが好きな方ほど、一度はそう考えたことがあるのではないでしょうか。
ご自身で庭木を手入れするDIY、とても素晴らしいチャレンジですよね。
実は、庭木の剪定で仕上がりを左右する最も重要なポイントが、剪定の「時期」なんです。
どんなに道具を揃え、切り方を学んでも、このタイミングを間違えてしまうと、木が弱ってしまったり、楽しみにしていた花が咲かなくなったりする可能性があります。
この記事では、DIYで剪定に挑戦したいと考えているあなたのために、庭木の種類別の最適な時期から、夏と冬での目的の違い、花や実を最大限に楽しむためのコツまで、プロの視点から分かりやすく解説していきます。
この記事を読み終える頃には、自信を持って剪定の計画を立てられるようになっているはずです。
不安なことがあれば、エクステリア専門会社 プラッツにご相談ください。
目次
1. 庭木剪定は時期がすべて!基本の考え方を解説します
「庭木の剪定、自分でやってみたい!」
そう思ってハサミを握るのは素晴らしいことですが、少し待ってください。
剪定において、技術以上に大切なのが「いつ切るか」という時期の判断です。
なぜ、そこまで「時期」が重要なのでしょうか。
それは、剪定が木にとって「大きな手術」のようなものだからです。
私たち人間も、体調が万全でない時に手術を受ければ、回復が遅れたり、体に大きな負担がかかったりしますよね。木も全く同じです。
木には、ぐんぐん成長する活発な時期と、活動を休めてじっとしている時期があります。
この生長のサイクルを無視して、例えば一番エネルギーを使う真夏に太い枝をバッサリと切ってしまうと、木は体力を一気に失い、ひどい場合にはそのまま弱って枯れてしまうことさえあるのです。
実際に私が受けたご相談でも、「夏にスッキリさせようと強く切ったら、翌年から元気がなくなってしまった」というケースは少なくありません。
また、花の咲く木の場合、知らずに剪定すると「来年咲くはずだった花のつぼみ」をすべて切り落としてしまうことにもなりかねません。
DIYでの剪定を成功させる秘訣は、この「木のサイクルに合わせた、負担の少ない時期を選ぶ」という基本の考え方を理解することに尽きます。
まずはこの大原則をしっかりと頭に入れておきましょう。
2. 【落葉樹・常緑樹】種類別の最適な剪定時期
ご自宅の庭木を剪定するにあたり、まず確認すべきなのは、その木が「落葉樹」か「常緑樹」か、ということです。
この2つのタイプによって、木の生長サイクルが大きく異なるため、剪定のベストシーズンも変わってきます。
【落葉樹】(冬に葉を落とす木)
代表的な種類:モミジ、ハナミズキ、アオダモ、ヤマボウシ、ウメ、サクラなど
最適な剪定時期:12月~2月
落葉樹は、葉をすべて落とした冬の期間、「休眠期」に入ります。
木の活動が完全にストップしているこの時期こそ、剪定の絶好のタイミングです。
休眠期に剪定するメリットは、木への負担が最小限で済むこと。
さらに、葉がまったくないため、枝の混み具合や全体の骨格が非常によく見えます。
「どの枝が不要か」「どう切れば理想の形になるか」を判断しやすく、DIY初心者の方でも失敗が少ない時期と言えるでしょう。
太い枝を切るような、少し大胆な剪定(強剪定)も、この時期なら安心して行えます。
【常緑樹】(一年中葉をつけている木)
代表的な種類:シマトネリコ、キンモクセイ、オリーブ、シラカシ、ツバキなど
最適な剪定時期:3月~4月、または9月~10月
一年中緑の葉を茂らせる常緑樹は、落葉樹のような完全な休眠期がありません。
そのため、剪定で木が受けるダメージが最も少ない、気候が穏やかな時期を選ぶのが鉄則です。
具体的には、本格的な成長期に入る前の春(3月~4月)か、夏の成長が一段落した秋(9月~10月)が適しています。
特に春の剪定は、切った後すぐに新芽が伸び始めるため、切り口の傷跡が早くふさがり、木が元気な状態を保ちやすいのでおすすめです。
逆に、真夏(7月~8月)や真冬(1月~2月)の剪定は避けましょう。
真夏は木が弱りやすく、真冬は切り口が寒さで傷んでしまうリスクがあります。
3. 夏と冬で目的が違う!それぞれの剪定と注意点
庭木の剪定は、主に冬と夏の年2回行われますが、それぞれ作業の目的が大きく異なります。
この違いを理解することで、より的確で効果的な剪定ができるようになります。
【冬剪定】(基本剪定・強剪定)
- 目的:樹木の骨格を作り、大きさを整える。
- 対象:主に落葉樹
- 内容:
木の活動が止まっている休眠期に行う、その木の基本となる形を作るための剪定です。
不要な太い枝を根元から切り落としたり、大きくなりすぎた木の高さを詰めたりと、少し大胆な作業が可能です。葉がないため枝の構造がよく見え、理想の樹形をイメージしながら作業しやすいのが特徴です。 - 注意点:
ウメやモクレンのように、春に花を咲かせる種類は、すでに枝に来年の花芽がついていることがあります。枝をよく観察し、丸く膨らんだ花芽をすべて切り落としてしまわないよう注意が必要です。
【夏剪定】(軽剪定)
- 目的:日当たりと風通しを良くし、樹形を軽く整える。
- 対象:主に常緑樹、茂りすぎた落葉樹
- 内容:
木が元気に成長している時期に行う、軽めのメンテナンス作業です。
勢いよく真上に伸びすぎた枝(徒長枝)や、内側に向かって生えている枝、他の枝と絡まっている枝などを間引くように切っていきます。これにより、木の内部まで日光が届き、風通しが良くなることで、病害虫の発生を予防する効果があります。 - 注意点:
この時期に冬剪定のような強い切り方をすると、木が深刻なダメージを受けてしまいます。あくまで「枝を透かして、風の通り道を作る」というイメージで、軽い剪定にとどめましょう。

4. 花や実を楽しむには?特別な木の剪定タイミング
庭の楽しみを彩る美しい花や、収穫できる果実。
これらを最大限に楽しむためには、剪定のタイミングに少し特別な配慮が必要です。
そのための黄金ルールは、「花が終わった直後に切る」ということです。
なぜなら、多くの花木は、その年の花が終わった後、少し経ってから「来年の花のもとになる芽(花芽)」を作り始めるからです。
この仕組みを「花芽分化(はなめぶんか)」と呼びます。
この花芽ができた後に剪定してしまうと、当然、翌年は花が咲かなくなってしまいます。
【春に咲く花木】
- 代表例:サクラ、ウメ、モクレン、ツツジ、ライラックなど
- 剪定時期:花が終わった直後~5月頃まで
- これらの木は、夏頃(7月~8月)に翌年の花芽を作ります。そのため、花が終わったらなるべく早く剪定を済ませるのが鉄則です。秋や冬に剪定すると、せっかくできた花芽を切り落としてしまうので注意してください。
【夏に咲く花木】
- 代表例:サルスベリ、ムクゲ、ノウゼンカズラなど
- 剪定時期:落葉期の冬(2月~3月)
- これらの木は、春に新しく伸びた枝に、その年の夏に咲く花をつけます。そのため、落葉して休眠している冬の間に古い枝や余分な枝を整理しておくと、春から勢いの良い新しい枝が伸び、結果として花付きが良くなります。
【実を楽しむ木(果樹)】
- 代表例:カキ、ミカン、ブルーベリーなど
- 剪定時期:落葉期の冬
- 果樹も基本的には、栄養を蓄えている落葉期に剪定します。不要な枝を整理することで、残した枝や実に栄養が効率よく行き渡り、より美味しくて大きな実がなりやすくなります。
このように、何を楽しみたいかによって剪定の最適なタイミングは変わります。
ぜひご自宅の木がいつ花を咲かせ、どんな特徴があるのかを観察してみてくださいね。
5. よくある質問:DIY剪定でよくある時期の疑問
ここでは、DIYで剪定に挑戦する方から、私が実際によく受ける質問にお答えします。
Q1. 「この時期だけは絶対に切っちゃダメ」というNGな時期はありますか?
A1. はい、あります。一般的に避けるべきなのは、木の成長がピークを迎える「真夏(7月下旬~8月)」と、寒さが最も厳しい「真冬(1月~2月)」の強剪定です。
真夏は、人間でいうと汗をたくさんかいて体力を消耗している時期。そんな時に大きな枝を切られると、回復できずに弱ってしまいます。また、高温多湿のため、切り口から病原菌が侵入しやすいリスクもあります。
逆に真冬は、切り口が寒風で乾燥したり凍ったりして、うまくふさがらずに木が傷んでしまう原因になります。
軽めの剪定ならまだしも、木の骨格を変えるような強い剪定は、この時期には絶対に行わないでください。
Q2. 台風シーズンが来る前に、枝を減らして折れないようにしたいのですが…
A2. 素晴らしい視点ですね。台風対策の剪定は、被害を防ぐために非常に重要です。
おすすめの時期は、本格的な台風シーズンを迎える前の6月~7月上旬、または9月頃です。
ポイントは、枝の数を減らして「風の通り道」を作ってあげる「透かし剪定」を行うことです。枝葉が密集していると風の抵抗をもろに受けてしまいますが、適度に枝を間引くことで、風が抜けやすくなり、枝が折れたり倒木したりするリスクを軽減できます。
ただし、この時期もあくまで軽剪定が基本です。木全体の形を小さくするような強剪定は避けましょう。
Q3. 何年も放置してボサボサになった木があります。いつ、どう切ればいいですか?
A3. 長年手を入れていない木は、枝が複雑に絡み合い、どこから手をつけていいか分からないですよね。
こうした木をいきなりバッサリと小さくするのは、非常に危険です。急激な環境の変化に木が耐えられず、枯れてしまうリスクが高まります。
セオリーは、2~3年かけて段階的に理想の形に戻していくことです。
まずは、木の活動が止まる落葉期(冬)に作業を始めましょう。1年目は、明らかに枯れている枝や、他の枝の成長を邪魔している太い枝を取り除く程度にとどめます。そして翌年、翌々年の冬に、少しずつ全体の大きさを詰めたり、細かい枝を整理したりしていきます。
焦らずじっくり取り組むことが、木にとっても安全な方法です。もしご自身で判断するのが難しい場合は、一度プロに頼んで基本の形にリセットしてもらうのが、最も確実で安心な選択肢と言えます。
6. まとめ:自信がない時はプロの技を参考にするのが吉
今回は、DIYで庭木の剪定に挑戦したい方に向けて、最も重要な「時期」というテーマを深掘りしてきました。
- 剪定は木の生長サイクルに合わせるのが大原則
- 落葉樹は冬、常緑樹は春か秋が基本シーズン
- 冬は「骨格作り」、夏は「メンテナンス」と目的が違う
- 花や実を楽しむなら「花後剪定」を忘れずに
これらのポイントを押さえるだけでも、剪定で大きな失敗をするリスクは格段に減るはずです。
自分で手入れした庭木が美しく整っていく姿を見るのは、何物にも代えがたい喜びと達成感がありますよね。
しかし、実際に木を目の前にすると、「この枝、本当に切っていいのかな?」「うちの木の種類がはっきりしない…」など、新たな疑問や不安が出てくることもあるでしょう。
そんな時は、決して無理をしないでください。大切な庭木を一度傷つけてしまうと、元に戻すのはとても大変です。
私たちのようなエクステリアの専門家は、木の特性や健康状態、お庭全体のバランス、そしてお客様が描く理想のイメージを総合的に判断し、最適な剪定計画を立てることができます。
株式会社プラッツでは、「この木一本だけ、手本として剪定してほしい」「自分では手に負えない高木だけお願いしたい」といったご要望にも柔軟に対応しております。
大切な庭木のこと、少しでも迷ったら、ぜひお気軽に私たちプロにご相談ください。あなたの庭づくりを、全力でサポートさせていただきます。
プラッツの施工事例は こちら